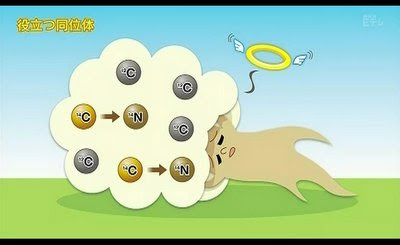La photographie, c'est la vérité.
写真が真実なら
映画は毎秒24倍真実だ

Studio Harcourt Paris
スタジオ アルクール パリ
「ここは1900年代初頭(1934)に生まれた、フランス写真史を代表するスタジオです」
En France, on n'est pas acteur si l'on n'a pas été photographié par les Studios Harcourt.
フランスでは、このスタジオで撮影しないうちは俳優ではない。
"In France, you aren't truly an actor if you haven't been photographed by the Studios Harcourt."
Roland Barthes(ロラン・バルト)
『Mythologies(現代社会の神話)』1957
 |
| l'ombre(影)と la lumière(光) |
「フランスの女優。キャロル・ブーケ(Carole Bouquet)よ。これを見ると、うちの写真の特徴がよくわかるわ。l'ombre(影)と la lumière(光)を表現しやすいモノクロ写真なの」
 |
| Photographie(写真)は『光で書く』という意味 |
「 Photographie(写真)は『光で書く』という意味。私たちも、光で顔を描いているの」
 |
| ろう人形を撮影した、真偽を問う作品 |
「これは le vrai et le faux(真偽)をテーマにした作品。ろう人形を撮影したの。世界的スター、シュワルツネッガーね。ここの写真には、自分と自分じゃない面がある真偽があって、それを楽しむの」
 |
| 白黒写真用のメイクにする |
「メイクに色はほとんど使いません。モノクロ写真だから。ピンクや緑ではなく、濃い紫、黒、グレーを使うの。照明も強いから、顔にキラキラ反射してダイヤモンドみたいよ」
 |
| 撮影の風景 |
「わたしが言うことはミリ単位。動くときはちょっとだけ。すごく細かいんです」
 |
| カメラ用のフラッシュは一切つかわない。使うのは映画用の照明、約10灯。 |
「ここで撮るのは、写真以上の体験と記憶。Image pour l'éternité (永遠のイメージ)です。スタジオには時間の概念がなく、別世界に誘われます。誰もが後世に美しい姿を残したい。そんな『永遠の美』を表しているのです」
 |
| 複数のカットから選ぶ。 |
「(写真を選ぶ)ポイントは、『時間を感じないこと』です」

Studio Harcourt Paris
"Leaving a trace, a glorious imprint, is the very raison d'être of the Harcourt photo."
美しい痕跡、刻印を残すことはアルクールの写真が担う使命
Francis Dagnan(フランシス・ダニャン)
スタジオ「アルクール(Harcourt)」の伝説は、1934年1月16日にはじまる。コゼット・アルクール(Cosette Harcourt)という一人の女性が立役者だ。
1930年代のパリ、スタジオ写真を学んでいたコゼットは、ジャック・ラクロワと出会う。そして設立されたスタジオ「アルクール」。その運営はコゼットに一任された。その評判はあっという間に広まり、パリ中の人々が自らの美しいポートレートを手に入れるべく、スタジオに詰めかけた。
第二次世界大戦がはじまると、コゼットはパリを離れざるをえなくなり、南仏、英国を転々とする。それでもスタジオは存続しつづけた。
フランスが解放されると、コゼットはスタジオに戻り、その後スタジオは黄金期をむかえる。ロラン・バルトが「フランスにおいて、スタジオ・アルクールで撮影をしないうちは俳優でない」と言ったのは、この頃のことである。
スタジオに翳りがみえはじめるのは、日本製の一眼レフ・カメラが登場してからだった。そんななか、1967年、コゼット・アルクールはその生涯を終える。その3年後、ジャック・ラクロワはスタジオを処分した。
以後、スタジオ・アルクールの所有者はたびたび変わってゆく。現在、フランシス・ダニャンの買い取ったスタジオは、カトリーヌ・ルナールの手によって運営されている。
Its traditions have been revived.
ふたたび伝統が重んじられることになった。
This provides crucial stability, and ensure a long-term future for the legendary Studio Harcourt, where the tradition of excellence has become a quarantee of timeless modernity.
こうして、いつまでも同じスタイルを保ち、神秘に包まれたスタジオ・アルクールの永遠性を守り続けることができた。秀逸を守る伝統は、時を超えたモダンの証しとなったのだ。
For an age, the "Harcourt Paris" label has stamped the portraits of celebrities and anonymous sitters alike with its assertive lettering, like a hieratic seal.
Harcout Paris のサインはいつでも、厳かな印章のごとく、著名人と一般顧客をとわずポートレートに威厳をもって添えられている。

出典:NHK語学 フランス語