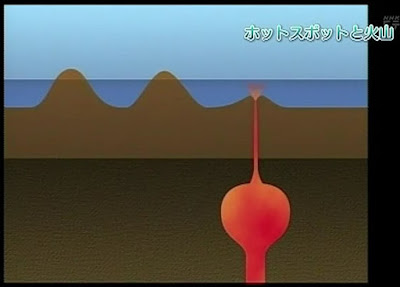米国外交の伝統:
American diplomacy
国務省軽視は大きな禍根を残す
A tradition traduced
(英エコノミスト誌 2017年4月29日号)
米国には誇らしく効果的な外交の伝統がある。それが今、貶められている。
The State Department is far from perfect.
But the administration's treatment of it is doing some real damage.
ほとんどの米国人は知らなかっただろうが、昨年の大みそかに米国の外交官たちは恐らく、中央アフリカで大量殺戮を未然に防いでいた。
Few Americans would have know it, but on New Year's Eve their diplomats probably prevented scores of killings in central Africa,
戦争を防いだ可能性もある。
and perhaps a war.
コンゴ民主共和国(旧ザイール)で長らく専制政治を続けているジョゼフ・カビラ氏は、大統領の任期が切れた後もその座にしがみついていた。
President Joseph Kabila, Congo's long-stay autocrat, had refused to leave power, as he was obliged to do.
これに腹を立てた人々が首都キンシャサの街頭に繰り出し、カビラ氏の治安部隊が出動しようとしていた。
Angry protesters were taking to the streets of Kinshasa and Mr Kabila's troops buckling up to see them there.
しかし、米国務省がアフリカ大湖地域特使として派遣していたトム・ペリエロ氏とジョン・ケリー国務長官(肩書はいずれも当時)が、価値観に基づいて行動する超大国の代表者らしい高潔な強引さと巧みな交渉術の合わせ技で説得にあたったことも手伝って、カビラ氏は折れた。
Yet through a combination of adroit negotiating and the high-minded pushiness that comes with representing a values-based superpower, Tom Perriello, the State Department's then special envoy for the Great Lakes, and John Kerry, the then secretary of state, helped persuade Mr Kabila to back down.
カトリック教会の仲介により、権力の共有と今年中の退任が約束された。
The resulting deal, brokered by the Catholic church, committed Mr Kabila to a power-sharing arrangement and retirement later this year.
実現すれば、コンゴでは初めての平和的な政権移行になる。
That would represent the first-ever peaceful transition in Congo.
だが、実現の見込みは薄い。
But it probably won't happen.
この3週間後、米国ではドナルド・トランプ氏が大統領に就任し、ケリー氏とペリエロ氏を含む100人あまりの政治任用職員が国務省を離れた。
Three weeks later, Donald Trump became president and the State Department's 100-odd political appointees, including Mr Kerry and Mr Perriello, shipped out.
米国の政権交代では普通に見られる光景だ。
That is normal in American transitions.
しかし今回は、トップクラスの職業外交官も任を解かれた。
But the most senior career diplomats were also pushed out,
これは普通ではない。
which is not.
しかも今のところ、新たに国務省にやって来たのはケリー氏の後任で、石油会社エクソンモービルの元経営者として名高いレックス・ティラーソン氏だけだ。
And only Mr Kerry has so far been replaced, by Rex Tillerson, a well-regarded former boss of Exxon Mobil.
ティラーソン氏は国務長官になろうという野心など持っておらず、そのポストに就くために面接を受けていることもトランプ氏に言われるまで知らなかった。
He had no ambition to be secretary of state -- or knew he was being interviewed for the job -- until Mr Trump offered it to him.
米国の外交政策の代弁者になったティラーソン氏は、長官としての資質を備えていることは間違いないにもかかわらず、公の場であれこれ詮索されるのを嫌うという、石油会社の社員のスタイルを維持している。
Now installed as the voice of American foreign policy, he has maintained, notwithstanding his undoubted qualities, an oilman's aversion to public scrutiny.
ティラーソン氏は記者会見を開いたり、外国訪問の際に現地の米国大使館を訪れたりすることはめったにない。
He rarely speaks to journalists or visits American embassies on his trips abroad.
トランプ氏が連邦議会に近々提案する国務省予算31%削減案の調整という、厄介な仕事のことで頭がいっぱいのようだ。
He appears absorbed by the ticklish task of arranging a 31% cut in his department's budget, which Mr Trump will shortly propose to Congress.
…